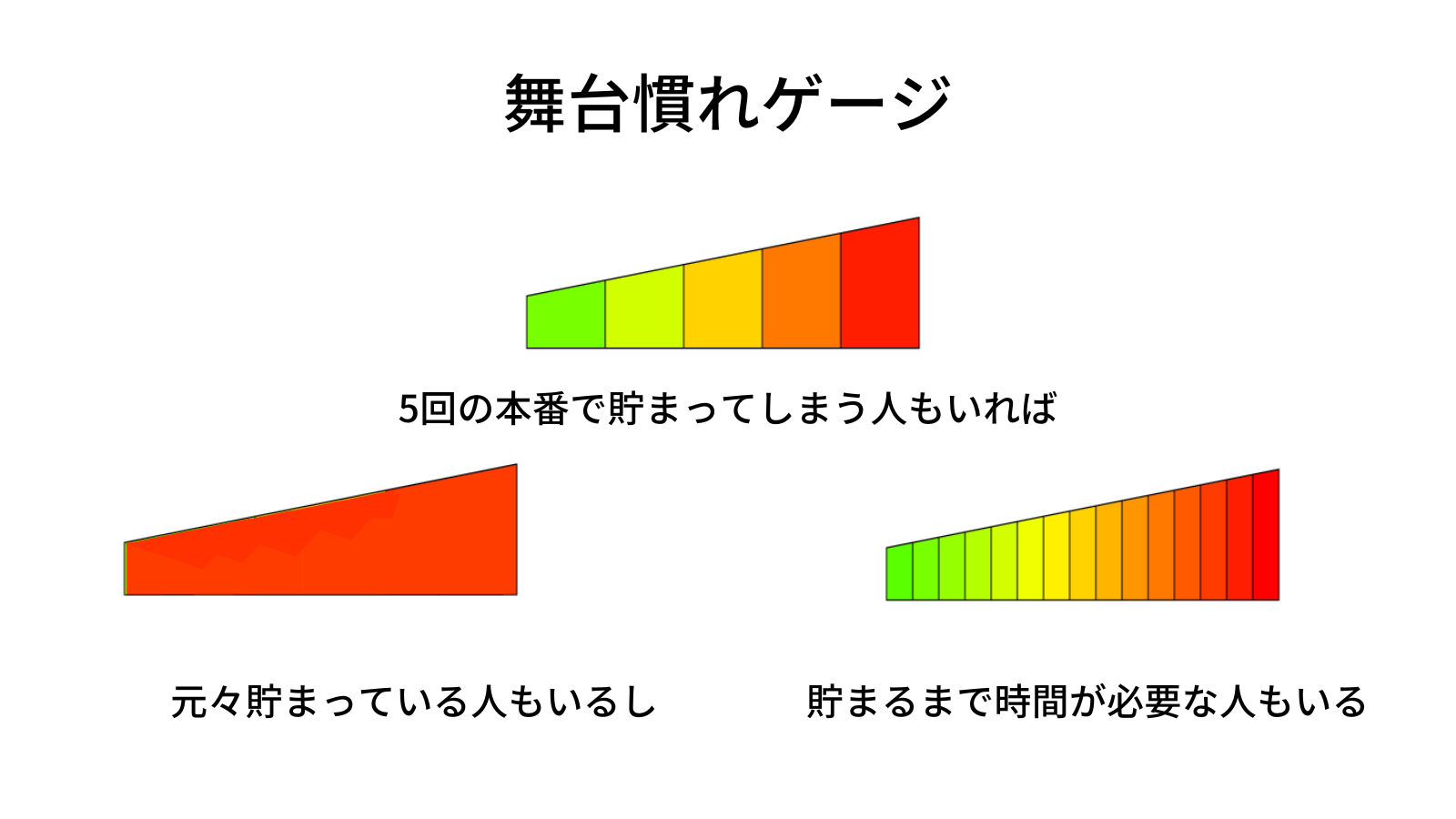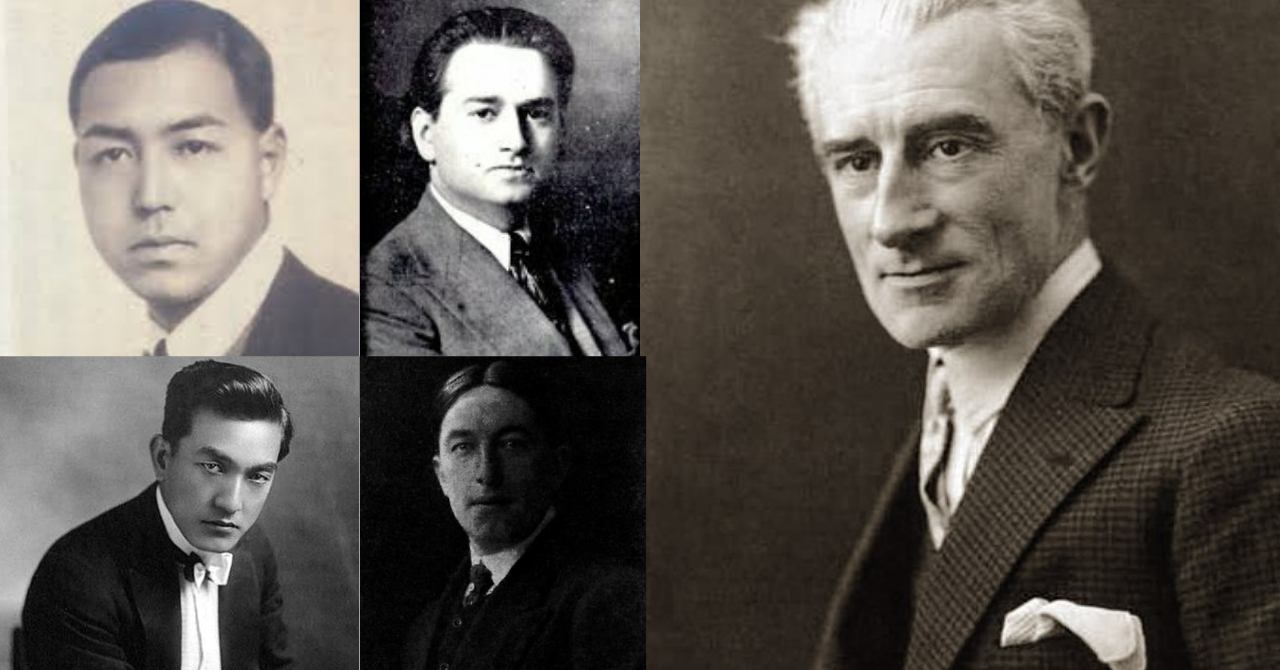グリゴリー・ソコロフについてピアニストの私が語ってみる③新しいCDの批評
さて、前回の記事の最後で触れた「ガーディアン紙によると星3つという酷評」の新しいCDについて今回は語ろうと思う。これは私の習っている教授の門下生チャットグループで「ガーディアン!お前は何様なんだ!!!」とクラスメートが荒れるくらい、私や一部のソコロフファンにとっては衝撃的なレビューだった。
ガーディアン紙の言い分
記事の出だしでは、私の第一回目の記事にも書いたようにどうしてソコロフが2007年以降イギリスに来ないのかについてチラっと触れてある。『今日存命する最も素晴らしいピアニストの一人』とも書いてあるし、ガーディアンは誰の事を批評しているかをちゃんと判っているようである。
その後には『ソコロフはバッハから20世紀の音楽まで弾くと言われているが、DGから出ているアルバムはメインストリームなレパートリーが多いぞ』というような文章に続き、今回のアルバムに収録されている作曲家の名前が連なっている。『初期、後期のベートーヴェンとそれに続いて後期のブラームス、そして幅広い時代をカバーしている7つのアンコール曲のラモー、シューベルト、ドビュッシーとラフマニノフ;2枚組CDセットを買った人にはボーナスでベートーヴェンの作品90と作品111のソナタ、モーツァルト、シューマンとショパンを弾いているソコロフが観れるDVDも付いてくる』みたいなことが書いてある。
さて問題の批評パートだが、出だしの紹介文やその次のCDの内容の説明と同じくらいの長さなのである。星3つを付けておいてそれはないだろう、と思ってしまう。
ざっくり日本語訳をするとこんな感じだ。『演奏はむらがあり、ベートーヴェンの演奏はブラームスより著しく説得力がある。宝石の幾つかはラフマニノフのg# minorのプレリュードやシューベルトのc minorのアレグレット、ドビュッシーの前奏曲’雪の上の足跡’ 等のアンコール曲の中に潜んでいる。ベストな演奏はCDの最初の方で、ベートーヴェンのソナタ作品2-3の演奏では若いベートーヴェンが古典派のソナタ形式の限界を試していた感じが非常によく伝わってくる。ベートーヴェンのバガテル 作品119の演奏も(作品2-3と同じような)凝縮された獰猛さ(または激しさ)を思い起こさせるが、淡々としていることもある。例えば作品118のいくつかの小品もそうだが、ブラームスはがっかりさせるくらい荒っぽく演奏されている。または、作品119の親密さは静寂で詩的な美しさにより作られるのにそれもソコロフの演奏には欠けている。』日本語訳は私が勝手に作ったので、少々稚拙なのはお許しください。
実際にCDを聴いてみた私の言い分
というわけでガーディアン紙的にもイチオシのベートーヴェンのソナタだが、私が聴いた限りではfierceness(獰猛さ)というよりかはprecision(精密さ)accurancy(正確さ)の方が近いかなぁ、と正直思った。若いベートーヴェンがこのソナタの中で行った"testing out the limits of classical sonata form"(古典派のソナタ形式の限界を試すこと)といえば、第一楽章のコーダ部分(ざっくり説明すると、曲の最後のところらへんのことです)にピアノ協奏曲に出てくるようなカデンツァを入れていたり、そもそものつくりが3楽章制ではなく4楽章制であることが挙げられる。そういう感じがメインで伝わってきたというよりかは、細かいピースを完璧にはめ合わせて一つの端正に美しい建造物を作っているような感じが私が聴いた時の印象であった。そもそもソナタ形式云々っていうのは演奏の評論になり得るのだろうか?私としてはソナタ形式の限界云々よりも、ソコロフの緻密で細やかなところをきっちりと完璧に演奏し、それでいてベートーヴェン特有のどこかから突き上げてくる衝動的なパワーも失わず、更に第二回目にも書いたように絶妙過ぎるテンポでまとめているところこそ特筆すべきことだと思った。この曲を勉強していた桐朋の高等科に入学したばかりの頃の私に「この演奏を聴いて勉強しなさい」と言ってやりたいものである。
ベートーヴェンのソナタにしろバガテルにしろ、ガーディアンはもう少し突っ込んだことは書けなったのか、と思ってしまう。一応「今日存命する最も素晴らしいピアニストの一人」に星を3つだけしか与えていないのだから、matter-of-fact(事務的な)以外にも何か言うことがあるはずである。そういう私だが特にバガテルに関して、ソコロフの音の美しさは時節現れる素朴でシンプルなフレーズでより際立つな、と改めて感心させられた。ソコロフ本人もインスパイアされたピアニストの一人にリパッティの名前を挙げているのだが、その音のクリアさと飾らないフレーズでより目立つ美しさは両者に通ずるものがある。
さて問題のブラームスだが、「この作品119の1を聴いてもまだ詩的さが足りないと言えるなんてガーディアン紙と私は果たして同じCDを聴いたのか」、と少し疑ってしまった。出だしの下降する音型を聴いた瞬間に、私の脳裏には『過ぎ去った過去の思い出に心を馳せながら、静かに「ほろり」と涙が頬をつたっている様子』が浮かんだ。これを聴いた人全員が私と同じことを瞬間的に想起するとは言わないが、これを詩的と言わずに何という、と私は強く感じたのである。
作品118にも119にも言えるのだが、まるで今から40年くらい歳を重ね、酸いも甘いも嚙み分けた私が、ある天気の良い秋の日に庭の木の落ちていく葉を眺めながら自分のこれまでの人生を回想しているような...そんなシチュエーションがよく合う演奏なのである。どの曲の根底にも深い温もりがある。それでいてハッとするほどノスタルジックで、情熱が湧き上がる時は決して短絡的ではなく、まるで内に秘めている炎がどんどん熱くなっていくようである。荒っぽい印象は特に無かった。
結論
ガーディアン紙こそ荒っぽい批評を書かないためにも、詩的な美しさをソコロフの演奏から学んでみてはいかがでしょうか。
おまけ
それにしてもソコロフのCDは2015年のものもリサイタルのライブ録音だったし、恐らくレコーディングスタジオで録音をしたくないタイプのピアニストなのだろう。何時間も一つの場所にこもって自分自身の演奏を録音したことがある人は分ると思うが、録音という作業はあまりに非人間的すぎる。私も先日音楽院の卒業試験の代わりに録音をする機会があったのだが、お客さんの熱や空気が全く感じられない中、ひたすら機械に向かって弾き続けるのは精神的にかなり堪えたし、出来上がったものもなんかなぁ、ライブの方が上手く弾けるのになぁ、とスッキリしない感じだった(それは私の技術不足も原因だと思いますが。)
今回紹介したCDだが、なんとYouTubeに全部音源が載っているのを発見した。グリゴリー・ソコロフ - トピック というチャンネルからCDの曲が全て聴けるで、この記事を読んで興味が湧いた方は是非CDを聴いて感想を教えて頂けたら私としても嬉しいです。
おまけ2 ソコロフって実際どんな人なの?
毎回コンセルトヘボウの楽屋に終演後に押しかけて、写真を撮ってもらったりサインまで頂いたり(この記事のヘッダーのフランクの楽譜がそうですね。家宝です。)、ファンサービスはなかなかいい方だと思う。写真を撮る時もちょっとお堅めだけどスマイルしてくれるし、どれだけ演奏が素晴らしかったかを伝えたら写真の二倍くらいニッコリして喜んでくれた。何よりアンコールをいつも6曲くらい弾いた後に、勝手に楽屋に押しかけてくるファン(それも廊下に溢れるくらいの量)の相手を一人ひとりしてくれるなんてとっても親切である。こういう風に優しくされると余計に、もっと応援しよう、来年も絶対来よう!、とモチベーションが爆上げするのである。
全く内容が同じ記事はこちらのリンク(noteの記事のリンク)からも読めます。