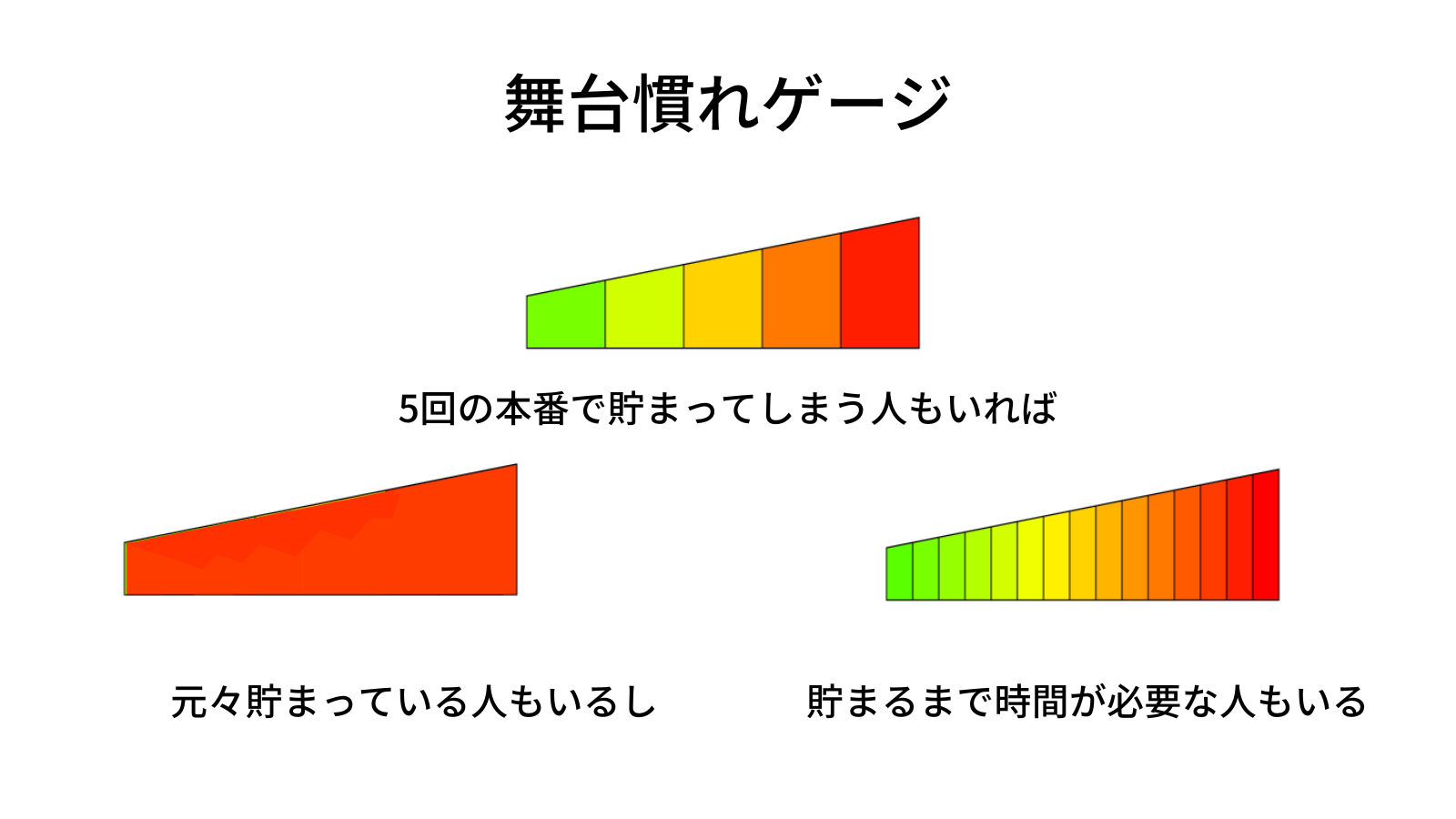ラヴェルと日本③ラヴェルの友人、ストラヴィンスキー
前回から引き続きラヴェルの友人たちに焦点を当てているこのシリーズだが、第3回目の今回は1910年代のストラヴィンスキーとラヴェルについて語ってみようと思う。
3つの日本の抒情詩について
あまり語られることのないストラヴィンスキーの作品に、『3つの日本の抒情詩(3 Poésies de la lyrique japonaise, 1912-1913)』というものがある。この曲は、センセーショナルで天才的な『春の祭典』と同じ時期に作曲されたので、どうしても日の目を見ない。なので第三曲目の『貫之』がラヴェルに献呈されていることもあまり知られていない。更に、第一曲目の『赤人』はドラージュに、第二曲目の『当純』はフローラン・シュミットにと、どちらもアパッシュの作曲家たちに献呈されている。勿論、この作品も音楽における初期のジャポニスムの表れと考えて良いし、同時に、当時のストラヴィンスキーがいかにパリでアパッシュのメンバーと親しく交流していたかが伺える、彼のあまり注目されない一面に光を当てる作品でもある。
ストラヴィンスキーは、A・ブランタによるロシア語訳された和歌(万葉集と古今集から)を歌詞に用いた。船山隆氏の著書『ストラヴィンスキー―二十世紀音楽の鏡像』に、松下大三郎氏の国家大観(角川書店)からの引用でオリジナルの和歌が掲載されている。
≪赤人≫ わが夫子に見せんと思ひし梅の花 それとも見えず雪の降れれば
≪当純≫ 谷風にとくる氷のひまごとに 打ち出づるなみやはるのはつ花
≪貫之≫ 桜花さきけらしなあしひきの 山のかひよりみゆる白雲
『ストラヴィンスキー―二十世紀音楽の鏡像』の第三章では、各々の短歌の特定をもっと掘り下げた形で船山氏が書いているので、興味のある方はそちらを是非読んでみて欲しい。
さて、作曲時期が1912-1913年であり、日露戦争(1904-1905)の後であることが個人的には非常に興味深い。20世紀初頭にもなると、日本は軍事的に力をメキメキと付けていった頃であろう。そんな日本に対してヨーロッパ諸国は、第一次世界大戦の頃までにはすっかり「極東の国への幻想」を拭い去っていった(そして、それがジャポニスムの衰退にも繋がっていった)ものだと私は思っていた。ストラヴィンスキーが1910年代にこの曲を作曲したことに関して、「歴史の流れを見てもどうして敢えてこの時期に?」と論文の指導教官と一緒に疑問に思ったのだが、船山氏が著書の中で述べているように、「音楽の発展が美術や文学にいくぶんおくれをとることは音楽史の法則である」、これが答えなのかもしれない。
3つの日本の抒情詩とラヴェル
さて、ストラヴィンスキーが『3つの日本の抒情詩』を作曲し、アパッシュのメンバーに献呈するに至った動機は何であろうか。答えは、当時のストラヴィンスキーとラヴェルの関係にあるかもしれない。ストラヴィンスキーの息子、テオドール・ストラヴィンスキーの著書(というかフォトアルバム) "Catherine and Igor Stravinsky: A Family Album"の中で、テオドールは以下のように書いている。
“A common taste for Japanese art and the similarity of their researches into
aesthetics at that time formed the substance of the friendship between Ravel and Stravinsky.” (私の勝手な日本語訳: 当時のラヴェルとストラヴィンスキーの友情の本質を築いたのは、日本の芸術への共通の嗜好と、その美学への類似した探求であった。)
なるほど、ラヴェルは日本の芸術に興味があり、それだけではなく、「美学への探求」までしていたわけである。更に船山氏は著書の中で、
1910年代のストラヴィンスキーと「アパッチ族」は、何度も繰りかえすことになるが、当時のパリのジャポニスムの熱心な信奉者であったのだ。
と述べている。確かに、他のアパッシュのメンバーであるドラージュは1912年に父親と日本を訪れているし、ロラン=マニュエルによるとラヴェルは1911年には当時住んでいたアパートメントに2枚の日本画を所持していたそうだ。(参考文献: Roger Nichols, Ravel remembered, 1987, p.141)
その後、ラヴェルがモンフォール・ラモリー市に家を買ってから、その玄関を浮世絵で埋め尽くし日本庭園を造っていたりすることを考えると、確かに1910年代時点でのアパッシュのメンバーの中にはジャポニザンが居たようだし、探せばもっと出てきそうである。
ジャン・パスラーの"Stravinsky and the Apaches"という文献によると、ドラージュが日本からパリに帰ってきた際、ストラヴィンスキーはドラージュから日本の版画を借りたり、1912年の夏にはドラージュのフランス語訳を助けに、ストラヴィンスキーは日本語で書かれた文章の勉強まで始めたそうだ。その文章のうちの3つが、『3つの日本の抒情詩』となったのである。
ドラージュとラヴェルはとても親しかった。船山氏の著書からの以下の引用や、『3つの日本の抒情詩』の作曲された背景を考慮しても、ラヴェルの周りの作曲家は相当日本の芸術に興味を持っていたことが伺える。 (そして、第二回目で書いたアンゲルブレシュトも、アパッシュのメンバーでありラヴェルの身近な音楽家であったことを忘れてはいけない。)この状況がラヴェルの作品に全く影響していないとは言い難いのではないか、と私は考えている。
(前略)「アパッチ族」の溜り場に逗留したストラヴィンスキーは、旅行から帰ってきたばかりのドラージュからジャポニスムの決定的な洗礼をうけ、ウスティルクでこの作品の作曲に着手し、ベルリンでシェーンベルクの《ピエロ・リュネール》を聴いた後に、クラランで《3つのマラルメの詩》を作曲したラヴェルとともに、この作品の作曲を続けた。
今日の結論
とは言ったものの、ラヴェルの『日本の芸術への嗜好』や『その美学への探求』がどのように彼の作品に表れているのかまでは、ここまでの私の研究では分かっていない。そもそも、「こんなに状況証拠が揃っているんだから、ラヴェル、おまえの作品は何かしら日本の芸術から影響を受けているはずだ!」と断言してしまうのはただの暴論である。しかし、可能性としては否定できないので、このシリーズは続いていくわけである。次回以降は、ドラージュとラヴェルについて、そしてラヴェルの家に行ってきた話や、ラヴェルが実は日本の音楽を聴いたことがある、という話等を追って書こうと思っている。
特別コーナー:私のお気に入りのラヴェル作品
今回は、ラヴェルがストラヴィンスキーの『3つの日本の抒情詩』と同じ頃に作曲した『ステファヌ・マラルメの3つの詩』を、憂いを帯びたアンニュイな声で歌い上げるオッターの録音でお楽しみください。
この少し鬱っぽくて、影が差したような、それでいて昇天していきそうな浮遊感が溜まらなく美しいです。ふとすると彼女の声が背後の室内楽に溶けて一体化してしまいそうで、その非現実的で神秘的な響きは白昼夢そのものです。外を歩きながら聴いた日には恐らく車に跳ね飛ばされるくらい魔力が強い演奏なので、くれぐれも室内でお楽しみください。