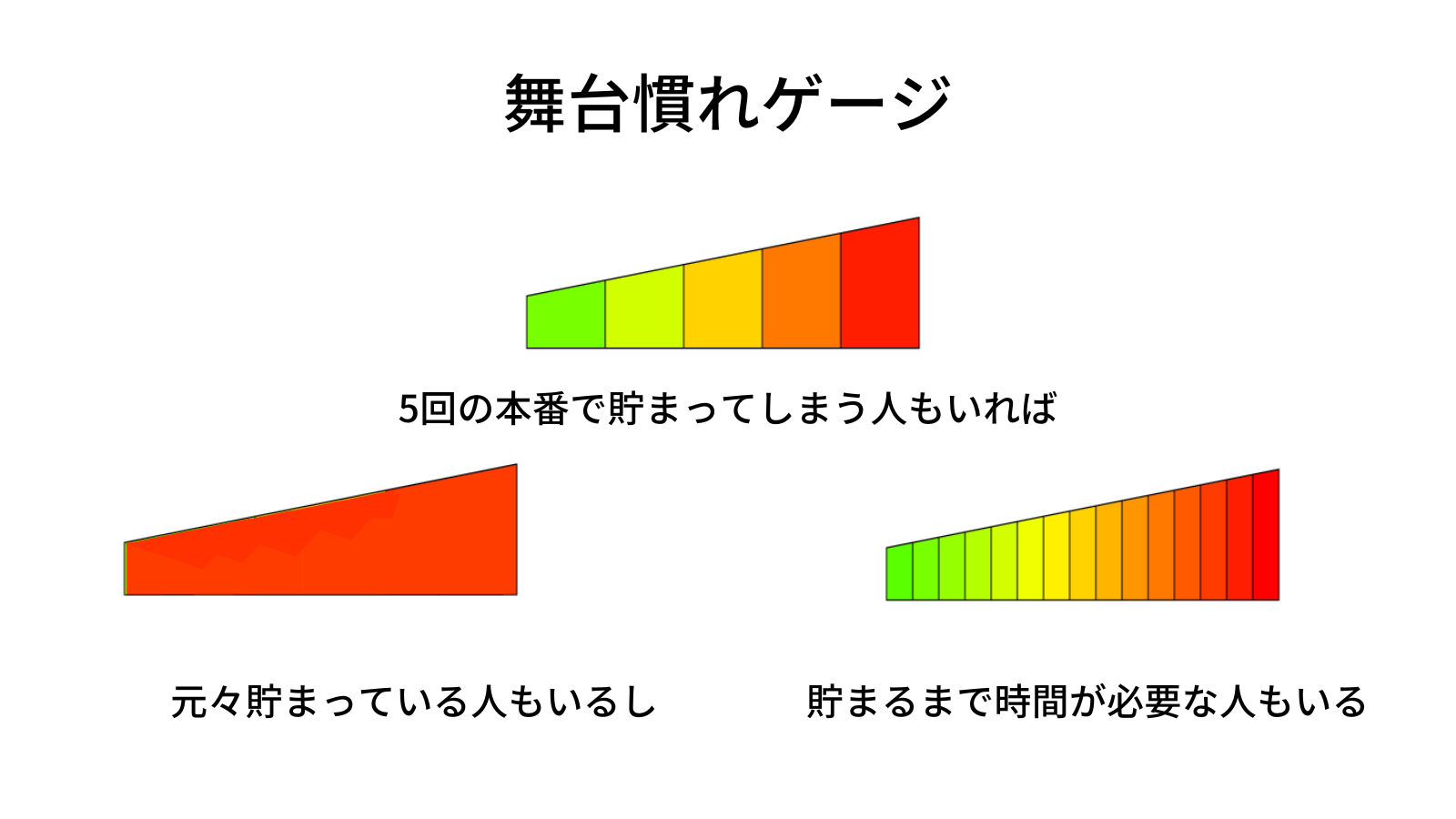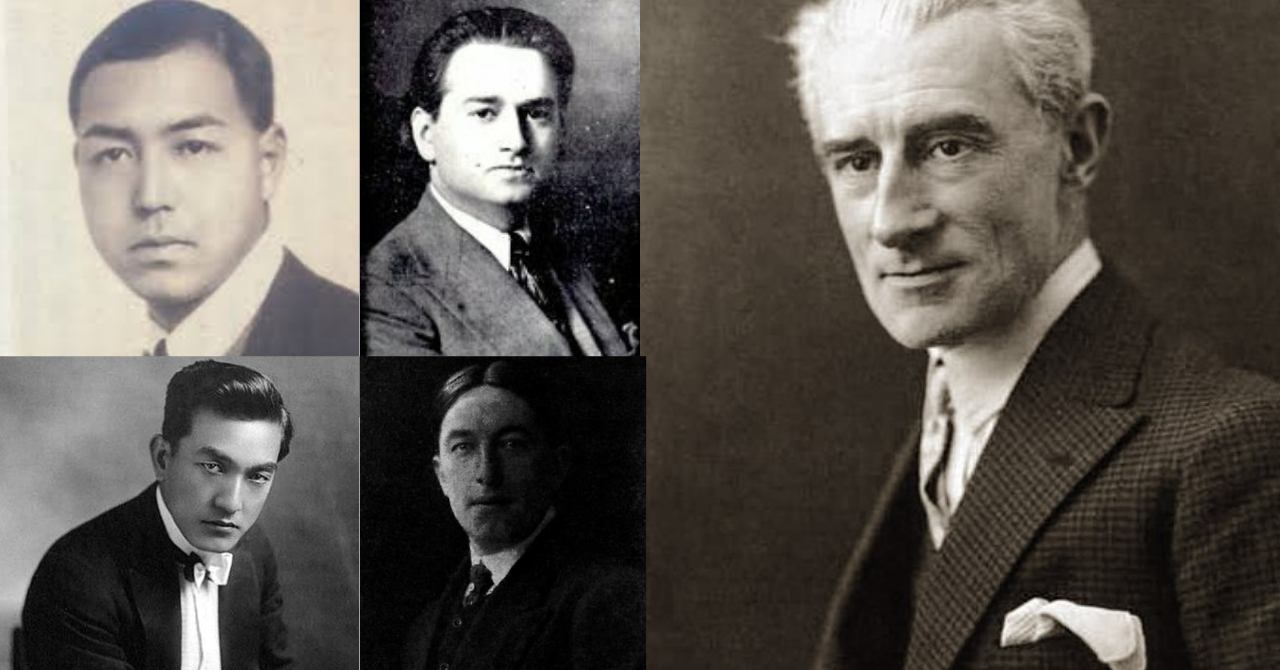シューベルト/ゲーテの『魔王』の魔王の正体は父親である理由
このドイツ歌曲の傑作中の傑作に関して、(ネットに落ちている)日本語で書かれた解説記事の殆どがあまりに浅い解釈であることに正直驚いた。私はドイツ文学者でも心理学者でも何でもないただのピアニストだが、ゲーテの詩の『魔王』、そしてシューベルトの歌曲の『魔王』どちらもこよなく愛している一人の音楽家として、私なりに本当の『魔王』とはどういう話なのかをここに書こうと思う。
ゲーテという詩人はあなたの想像以上に変態だった
早速ネタバレなのだが、私はこの『魔王』で描かれているのは魔王(正体は父親)が自分の子供をレイプする話だと解釈している。そのことを一緒に活動していたソプラノの友人に話してみたら、「この曲の中にはそういう性的なことは一切表現されていないし、誰もレイプされていない。ゲーテの詩を読めば一目瞭然だ。そもそも、時代が今と詩が書かれた頃じゃ全然違う。」と言い返されてしまった。カトリック教会が少年を犯す話はここ数十年に始まったことではないし、もっと遡ると古代ギリシアでは少年愛に美や善を見出していたくらいなので、今も昔も性に関して人間は余り変わっていないよ...という反論はさておき、これを読んでいる皆さんも、「魔王は伝説上の存在であり、詩中のどこにもレイプの描写なんてないじゃないか、それにゲーテってそんな詩を書く人間だったのか?」と思ったのではなかろうか。
ゲーテは『ファウスト』や『若きウェルテルの悩み』で有名なドイツの詩人で、科学者、政治家、法律家と何でもできた天才である。しかし「凄い人」というイメージばかりが独り歩きしてしまい、実は卑猥な詩もあることはあまり知られていない。
彼は当時の基準からしてみたらセックスに関してかなりオープンで、“Das Tagebuch“ という作品の中ではナレーターの男性器のことを"master"と形容し、さらにそのマスターが勃起を拒む様子まで描写している。1810年に完成したこの作品は、そのあまりに猥褻な内容のせいで1861年まで出版されず(しかし全文では無く過激さのトーンを落とした形でだった)、1914年にドイツ語での原文の全てがやっと出版されることになる。そして1968年に、かの有名なアメリカの成人向け雑誌『プレイボーイ』に英語訳全文が掲載された。
他にも、Römische Elegien(英: Roman Elegies ローマの悲歌)という作品はそのあまりに精密な性描写により検閲にひっかかり、ゲーテの死後1914年になって初めて発表された。これは検閲に引っかかっても仕方がない、という衝撃的な一文をRömische Elegienから引用しよう。
"I'm fairly fond of boys, but my preference is for girls; When I have enough of a girl, she serves me still as a boy." (私による勝手な訳: わたしは男の子が好きだが、私の好みは女の子である。女の子を十分味わったら、彼女は男の子としてわたしを満足させる。)
まあつまり、男も好きだけど女の方が好きで、女の子とやることやってもう充分ってなったら、女の子のお尻の方で楽しいことをすればいいし、みたいなことが書かれているわけである。
まとめると、ゲーテという詩人は積極的に性に関するあれこれを表現する、かなり型破りな詩人であった。勿論ただ直接的に表現してばかりいては、最近の半裸で愛やらセックスやらを歌い上げるアメリカのポップシンガーと変わらない。芸術的に表現できるのがレディー・ガガとゲーテの違いである。
魔王でのゲーテのドイツ語のチョイスをドイツ人と考えてみた
ここからは肝心の『魔王』の詩の内容を考察していこうと思う。私事だが9日後くらいにドイツ人男性と入籍する。常日頃から口うるさく「ゲーテはドイツ語で読まなきゃ良さが解らない」「ゲーテはドイツ文学の最高峰」と言っている彼と一緒にドイツ語でこの詩を読んでみた。ここにドイツ語の詩全文と英語訳、そして一般的な解釈であろう日本語訳のリンクを貼っておく。以下におおまかな詩の流れを日本語訳のリンクから引用し、ドイツ語訳のミスなどを指摘していく。
登場人物は4人、ナレーター、男児、父親、魔王である。まず、ナレーターが「こんな遅い夜に風をきり馬に乗っているのは誰だ? それは父親と子供 父親は子供を腕にかかえ しっかりと抱いて温めている」と物語を始める。
そして父親が「何がそんなに怖いんだ」と子供に聞き、子供は「お父さん、魔王が見えないの?王冠とシッポをもった魔王が」と返す。ここで尻尾と訳されている単語 Schweifだが、ドイツ人の説明によると「Schweifは尾でもあるし、彗星でもあり得る。尾を引くような長いものっていう意味合いだけどこの場合はただの尻尾だろうね。」とのこと。とっさに「尾なら男性器を模しているのではないか」と聞いてみたのだが「それは深読みしすぎ」と言われてしまった。ただ、後日見つけたこの記事には"Erlkönig has a crown and a symbolic, phallic tail."(魔王は王冠と、象徴的な男根の尾を持っている)と書いてある。うむ、個人的には少し深読みの気がしないわけではない...
そして父親は「息子よ、あれはただの霧だ」と言い、魔王のパートが始まる。因みに霧と訳されているNebelstreifは正しく訳すと霧峰(きりみね、霧の層)である。その次から始まる魔王の「可愛い坊や、私と一緒においで 楽しく遊ぼう キレイな花も咲いて 黄金の衣装もたくさんある」は明らかに男児を誘惑しているのだが、これに恐怖を感じた子供が「お父さん、お父さん!魔王のささやきが聞こえないの?」と言っても父親の方は「落ち着くんだ坊や 枯葉が風で揺れているだけだよ」と気にも留めない。そしてまた魔王のパートが始まる。「素敵な少年よ、私と一緒においで 私の娘が君の面倒を見よう 歌や踊りも披露させよう」これもまた男児を誘惑しているのである。
この魔王のパートを読んだ時、私が7歳くらいの頃公園で遊んでいたら、中年男性二人組に「君可愛いね、お菓子あげるから、あそこにあるおじさんの車に乗って、広いところでかくれんぼしようよ」とマーブルチョコレートを渡されて、慌てて家に帰ったことを思わず回想してしまった。いつの時代も悪い人が子供を誘惑する方法は変わらないということか。
そして男児が「お父さん、お父さん!あれが見えないの?暗がりにいる魔王の娘たちが!」と言うのだが、相も変わらず父親の方は「息子よ、確かに見えるよ あれは灰色の古い柳だ」という。そしてまた魔王が出てきて「お前が大好きだ。可愛いその姿が。いやがるのなら、力ずくで連れて行くぞ」と言うのだが、ここの訳のせいでこの詩は正しく理解されないことが多い。
魔王の最後の台詞"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt."は紛れもなく魔王によるレイプの宣告である。一つずつ訳すと、Ich liebe dich(おまえを愛している)mich reizt deine schöne Gestalt(おまえの体はわたしを性的に興奮させる)→ reiztは英語にするとexcited(興奮する)やaroused(性的に興奮する)といった意味になる。ゲーテが他の単語を選ばず、性的に興奮するという意味を持った語を選んでいる時点で、ここで魔王がどんな状態にあるかは一目瞭然だ。Gestaltはドイツの哲学者が大好きな言葉の一つだが、ここではBodyと訳すのが自然だとドイツ人は言っている。Und bist du nicht willig(いやがるなら)so brauch ich Gewalt(わたしは暴力を使う必要がある)→Gewaltの意味はforceとも言えるが、violenceでもある。さらに、ドイツ語でレイプを意味するVergewaltigungという語にもGewaltが含まれている。
つまりここの魔王の台詞は「おまえを愛している。おまえの体はわたしを性的に興奮させる。いやがるなら わたしは暴力を使う必要がある。」というレイプの告知で間違いない。魔王の心境としては、散々優しくして気を引こうとしていたのに男児は一向に靡く様子も無く、もう我慢ができなくなって「それなら力づくで犯してやる」ということだろう。
その後怯えた男児は「お父さん、お父さん!魔王が僕をつかんでくるよ!魔王が僕を苦しめる!」と言う。父親からの返答は無い。その代わりにナレーターの「父親は恐ろしくなり 馬を急がせた 苦しむ息子を腕に抱いて 疲労困憊で辿り着いた時には 腕の中の息子は息絶えていた」で曲が終わる。この最後のナレータの台詞を「馬を急がせた(=急いで腰を振った) 苦しむ息子を腕に抱いて 疲労困憊で辿り着いた時には(絶頂を迎えた後には)腕の中の息子は息絶えていた」と解釈してしまうのも、深読みのし過ぎだと私は思うのだが...
シューベルトはどう詩を解釈したのか楽曲分析をして読み解いてみた
前項では詩の内容がWikipediaの言うように、魔王という超自然的な伝説上の生き物が病気の子供の命を奪う、という文面通りの内容ではなくて(そもそもどこにも『病気の』子供とは書いていない)魔王によるレイプが物語のクライマックスだということを確認した。ここからはどうして魔王=父親なのかをシューベルトの作曲を分析することで立証しようと思う。
(音楽の専門的な用語を使わないで説明することが難しかったため、仕方なく幾つかの用語が出現することとなってしまいました。どうかご了承ください。)
父親=魔王を証明するには、父親のパートの音楽的な役割を分析する必要がある。父親が出てくるところは、
①Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht(息子よ、何を恐れて顔を隠す?)
②Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.(息子よ、あれはただの霧だよ)
③Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt der Wind.(落ち着くんだ坊や 枯葉が風で揺れているだけだよ)
④Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau, Es scheinen die alten Weiden so grau.(息子よ、確かに見えるよ あれは灰色の古い柳だ)
の4か所だ。そのうち、②③④の直ぐ後に魔王のパートが始まる(①は子供→父親→子供の対話だ。)魔王はいつも父親の後に出てくるのである。因みに、子供と父親の間で会話はあるし、子供は魔王に反応をするのだが、父親と魔王の間には何の干渉もない。なぜ父親と魔王は対話しないのだろうか?父親と魔王が同じならそもそも会話もできないだろう。
さて、g minor(ト短調)で始まった曲はシューベルトらしく紆余曲折し、様々に転調するのだが、ここでは主に父親から魔王に変わるところ(②③④)の分析を紹介しようと思う。
まず②ではそれまでc minor(ハ短調)だったのが②の直前の子供の"Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?"(王冠とシッポをもった魔王が)から徐々に長調に移行しているのが伺える。ただ、この子供のパートではまだ長調に落ち着いたとは断言できず、父親の②のNebelstreifで初めてそれまでのピアノ譜右手のFの連打がB major(変ロ長調)のドミナントであったことが解かり、B major(変ロ長調)に落ち着いたことが実感できる。その後の魔王の"Du liebes Kind,"(可愛い坊や)からも同じくB major(変ロ長調)で、魔王が長調の優しい響きに乗せて誘惑しようとしているのが何とも気持ち悪い。
③では最初の半分の"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind"(落ち着くんだ坊や)がe minor(ホ短調)の五度の和音から属七の和音を経て主和音に落ち着き、最後の半分のIn dürren Blättern säuselt der Wind.(枯葉が風で揺れているだけだよ)ではなんとe minor(ホ短調)からC major(ハ長調)に転調している。その後の魔王の"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?"(素敵な少年よ、私と一緒においで)もやはりC major(ハ長調)に留まるのである。
つまり、父親のパートは音楽的には魔王のパートへの移行の役割があると言える。音楽的には父親のパートが魔王のパートへの橋渡しのようになっているからだ。父親が魔王に変貌している、とシューベルトが考えていなければ、どうしてこのような和声を展開したのだろうか?
そして極めつけが④である。ここで父親はやはりc# minor(嬰ハ短調)と短調で始まるのだが、劇的な和声の移り変わりを経てd minor(二短調)で終わる。あれ?なんで長調で終わらないの?魔王への移行を準備しているんじゃないの?と思った方がいるかもしれない。特筆すべきは、④のフレーズの終わりの"Weiden so grau."(音にすると ラ - ラ - ラ - レ)である(下の画像の楽譜の赤枠を参照。)
これが④の直ぐ後の魔王のパートの終わり方と全く一緒なのである。
魔王の方では"brauch ich Gewalt."(わたしは暴力を使う必要がある)とレイプ告知で終わっているフレーズだ。つまり、④で〈短調から長調に転調しなかった〉という過去2回とは違う終わり方をした父親のフレーズは、次に出てくる魔王の、レイプの告知部分との同じ終わり方によって説明される。父親はついに性的欲求を抑えられなくなり、今までは「何てことない」と落ち着いて子供をあしらってきたものの、ここで遂に爆発し本性が出るので長調に移行しなかった(移行できなかった)のではないか。そして魔王のフレーズは④のd minor(二短調)からなんと半音上がったE♭major(変ロ長調)へと強引に転調した先で「おまえを愛しているよ」と始まり、最後には「わたしは暴力を使う必要がある」で父親のフレーズの最後と同じようにラ - ラ - ラ - レ でd minor(二短調)に戻り台詞を終えるのである。
もう一度書こう、もしシューベルトが父親=魔王と考えていなければ、どうしてわざわざ、父親のパートの最後で一々転調をして魔王への準備をしたり、終いには父親と魔王の最後の台詞の終わり方を同じにして、あたかも父親と魔王が同じであるかのように作曲したのだろうか?
結論
詩というのはいつも文面通りに受け取っては本質を見失ってしまうと思う。例えばドイツ歌曲に度々登場するローレライという話は、恐らく先人の「綺麗な女の誘惑に乗っかると盲目になり破滅する」という教えも含まれているだろうし、物事の本質や教訓を直接的にではなく、人々が語り継ぎたくなるような魅力的な物語として後世に伝えるのはおとぎ話から聖書まで、古今東西どこでも同じである。
確かに魔王が伝説上の存在で、暗くて不気味な夜に子供の命をさらう、と詩の内容を受け取ることもできるが、詩で使われているドイツ語やシューベルトがどう作曲したかを見て分かったように、これはそんなに単純な話ではない。そして、小児愛という簡単ではないテーマを芸術作品として提示したゲーテは、過激な性描写で有名でもあった。『魔王』はゲーテだからこそ作れた傑作で、そこに隠れた意味を受け取ったシューベルトにより音楽で表現された。そしてそれを見事に、恐怖や不安感だけでなく「自分の子供をレイプする」という常識を逸脱した行為への『嫌悪感』を表現したのがディスカウの録音である。
今一度、詩の意味を理解したところでこの録音を聴いてほしい。彼の魔王はとても気持ちが悪い。これは詩の本来の意味を理解できてこその演奏なのである。
あとがき
YouTube上の色々な録音を聴いてみたが、個人的に一番良い録音がディスカウで、同じくらい素晴らしいのがクヴァストホフだった。全然好きではない録音もたくさん見つけたので、気が向いたら魔王の録音の批評を好き勝手に書いてみようと思う。